日本文化史講義4・日本文化史特殊講義Ⅳb 授業内講演「旧島津家本邸」

文化史学科研究室です。 ご講演中の古郡氏 日本文化史講義4・日本文化史特殊講義Ⅳb(どちらも同じ科目です)の授業では今年度でご退職される狐塚裕子先生が「島津山と清泉女子大学 」というテーマで授業をおこないました。 清泉女子大学のキャンパスは、かつて袖ヶ崎と呼ばれ江戸時代には仙台伊達藩の下屋敷でした。 明治維新後は元鹿児島藩主島津家の所有となり、大正期にはコンドル設計による洋館が建設されましたが、太平洋戦争末期には島津家の手を離れました。 戦後、GHQの宿舎、日銀の倉庫時代を経て、清泉女子大学の所有となり、60年が経過しました。 授業では由緒ある島津山の歴史を振り返りました。 1月20日(金)の授業では歴史ある、そして、学生さんたちの学び舎でもある旧島津家本邸についての授業内講演が開催されました。 講師は管理課の古郡信幸氏(文化財・施設設備コーディネータ)。 教室で古郡氏による旧島津家本邸の修理・改修を中心に講義を聴きました。 その後、場所を旧島津家本邸へ移し、屋根裏部屋の見学を始め、修理・改修された場所を実際に見て歩く本館見学ツアーが開催されました。 本館見学ツアー ガイド:古郡信幸氏 参加者:日本文化史講義4・日本文化史特殊講義Ⅳb受講学生28名 狐塚裕子先生、中野渡俊治先生(専門:日本史)、文化史学科研究室助手 ツアールート *旧島津家本邸は本館として大学関係者に親しまれています。 ルート紹介では「本館」という名称でご案内いたします。 補修したタイルについて 説明する古郡氏 ①本館外側 聖堂外側のタイル 本館を覆っているタイルは白ではなく、ほんのりクリーム色をしています。 2015年におこなわれた工事では、タイルを一枚ずつコンコンと叩き、接着面に生じた空洞の有無を調べました。あわせてタイルの破損状態を目視で確認し、約2,000枚のタイルを貼り替えました。 実際にタイルを見ましたが、古びた色合いに作成したため、素人的には当時のタイルと補修したタイルの見分けがつかないほどでした。 ②本館1階と1号館1階の連結部 今は通路となっている本館と1号館の連結部には窓がありましたが、これを撤去して通路をつくりました。 聖堂扉の上にあるレリーフの外枠のみを制作し、これを連結部の扉上に設置することによって、周辺とのデザインの統一を図っていま...


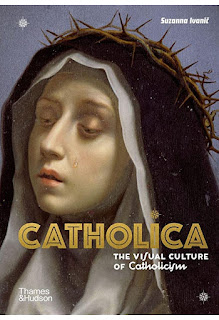

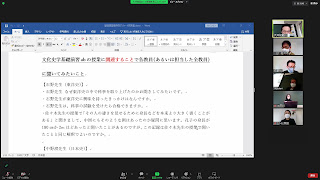
.jpg)