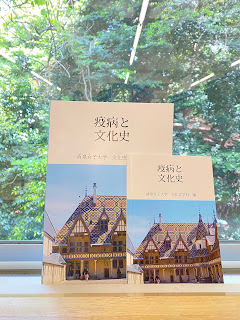文化史学科の学び紹介 Vol.2:女性史「歴史ミュージカルを使って、マリー・アントワネットについて学ぼう!」

文化史学科研究室です。 文化史学科には「女性史」という授業があります。 その名の通り、「女性の生涯を学ぶ」2021年度からスタートした比較的新しい授業です。 今年度はフランス王妃マリー・アントワネットとオーストリア皇妃エリザベートの生涯について学んでいます。 授業を担当されている大井知範先生(西洋史)より授業の様子が届きましたのでご紹介いたします。 女性史 担当教員 大井知範先生 マリー・アントワネットの生涯 (大井先生作成) 履修可能な学年 1~3年生 大井先生からのコメント 文化史学科の選択科目「女性史」も今年で3年目となりました。この授業では、フランス王妃マリー・アントワネットとオーストリア皇妃エリザベートの生涯を学び、時代や運命に翻弄されながらも力強く生きた女性たちの足跡を追います。 この授業の特徴は歴史ミュージカルを使い、感性と思考をフル稼働させる点にあります。ほかの授業でも、『レディ・ベス』、『モーツァルト!』『レ・ミゼラブル』など幅広い歴史ミュージカル作品を扱っていますが、ミュージカルは私たちの心を揺さぶりながら思考を促す「教材」となりえます。 学生のみなさんには、「感動こそが思考の出発点!」になることを意識して女性史の学びを深めていただきたいと思っています。 授業でミュージカル? 大井先生は様々な授業で歴史ミュージカルを教材として使われています。 女性史の授業ではミュージカルの場面を区切りながら観ていますが、過去には「スペシャル補講」と題しミュージカルを通して観る!という企画も開催されました。 ミュージカルを観るだけでなく、大井先生による解説や質問回答討論会、マリー・アントワネットベストソング投票結果発表などもおこなわれました。 約半日かけて開催された「スペシャル補講」についてはこちらのブログをご覧ください! https://seisenbunkashi.blogspot.com/2022/01/blog-post.html 授業を履修している学生さんからのコメント ハッピーエンドとは決していえないような結末を迎えた今回の作品でしたが史実を忠実に再現しているからこそこのような壮大で素晴らしいミュージカルが完成したのだと私は考えました。また、一般市民の代表として「マルグリット・アルノー」の存在が想像以上のキーパーソンとなり...

.jpg)